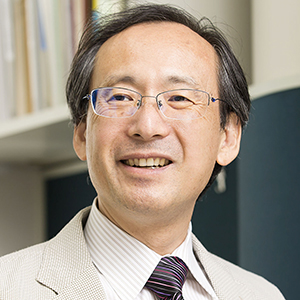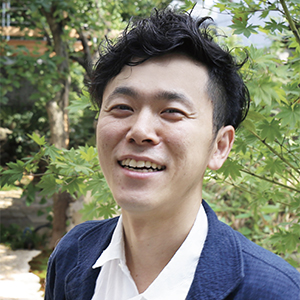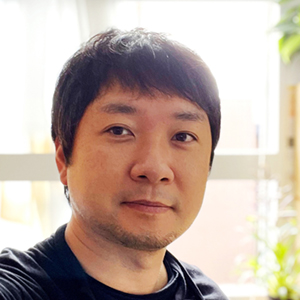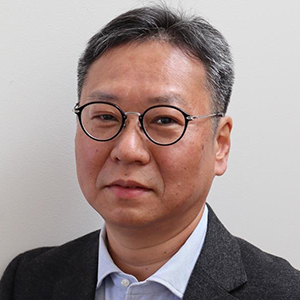写真1 トゥーゲントハット邸庭側外観(すべての写真撮影:筆者)
はじめに──ミースの代表作
前回は「無名の建物」を紹介したが、今回は対照的に、世界遺産の住宅をとりあげることにしたい。それは「トゥーゲントハット邸」(写真1)で、ルートヴィッヒ・ミース・ファン・デル・ローエ(1886-1969)の設計で1930年に竣工したものである。この建物は、チェコ第2の都市ブルノの高級住宅地に建てられた。その後幾多の変遷を経て、1994年から公開がはじまり、2001年に世界遺産に登録され、2010年から12年にかけて当初復原のための工事が行われた。巨匠の代表作ということだけでなく、モダニズム建築の保存に示唆を与えるものとしても注目すべき建物である。ここでは、MIES IN BRNO—TUGENDHAT HOUSE(Muzeum města Brna, 2018)と、The Rebirth of the Tugendhat House(The Heritage of Mies: Docomomo Journal, No. 56, January, 2017, pp.45-55)を参照しながら、この建物の歴史や見どころを紹介しつつ、モダニズム建築の保存についても考えることにしたい。
トゥーゲントハット邸の歴史
この建物は、フリッツ&グレーテ・トゥーゲントハット夫妻の新居として建てられた。トゥーゲントハット家もグレーテの実家レウ=ベーア家も、ドイツ語を母語とする裕福なユダヤ人の家系で、ブルノでウールなどの製造・販売を手がけていた。ブルノはウィーンから直線距離で100km強ということもあって、ウィーンの文化圏にあり、ウィーンの建築家がブルノで仕事をしたり、その一方で、ヨゼフ・ホフマン(1870-1956)のように、同地のドイツ系の工芸学校を経てウィーンの美術アカデミーで建築を学び、有名になったチェコの建築家もいた。なお、アドルフ・ロース(1870-1933)はブルノ生まれである。チェコは永らくドイツやオーストリアの支配下にあったが、ブルノでは、19世紀後半から街を囲む城壁を取り壊し、パリやウィーン、バルセロナのように、都市計画による改造が進められた。それにともない、繊維産業を中心に工業都市として発展し、1918年のオーストリア=ハンガリー帝国解体時にチェコスロヴァキアとして独立してからも、その流れは続いていた。そのような経緯から、ブルノでは産業資本家が上流階級を占めていただけでなく、1920年代にはモダニズムのカフェや集合住宅が建てられはじめていた。都市改造が進められていたので、建物を新築する機会が多く、産業資本家が、貴族や聖職者に代わって、建築家にとっての新たなパトロンになっていたのである。
フリッツ・トゥーゲントハット(1895-1958)とグレーテ・レウ=ベーア(1903-1970)は1928年7月にベルリンで結婚し、ブルノに家を建てて定住することにした。その設計をミースに頼むことを望んだのはグレーテである。この夫妻は美術に関心が深く、モダンな建築を欲していた。フリッツは自分で現像もするアマチュア写真家で、グレーテはドイツの美術史家・収集家のエドゥアルト・フックス(1870-1940)のベルリンの自宅のサロンの常連だった。そのフックスの家はかつてペルル邸(1913)だったもので、ミースが設計していた。グレーテは、ヴァイゼンホーフ・ジードルンク(1927)の出展住宅にも注目した。その住宅展を仕切ったのは当時ドイツ工作連盟の会長代理だったミースであり、彼自身もそこに集合住宅を設計していた。
トゥーゲントハット夫妻はベルリンでミースに会った。グレーテの回想によれば、ミースはそのときに、部屋の最適寸法は計算で割り出せるものではなく、そこに立ち、歩き回ることを想定して決めるものであり、ファサードは内部のあり方を反映するもので、窓は壁に空いた穴ではなく、床から天井まで開くものだといったという。そして、モダンな建物では高級な材料を使うことがいかに大事かを説いたそうである。
夫妻の招きに応じて、ミースは1928年9月にブルノを訪れた。この設計依頼を受けた当初、ミースはあまり乗り気ではなかったらしい。ブルノはベルリンから遠く、熟練工が得られるかどうか、わからなかったからである。しかし、その敷地が気に入っただけでなく、ブルノの新建築のデザインのレベルが高く、いい施工業者がいることを知り、すぐに設計にとりかかり、3カ月後のクリスマス・イブに基本設計を夫妻に見せた。
それは夫妻の想像をはるかに超えるものだった。規模は彼らが当初想定していたよりはるかに大きくなり、平面図には等間隔に小さな十字形(鉄骨柱)が描かれていた。また、建具が床から天井まで通しの1枚になっていることにも驚いた。それではたわんでしまうのではないかと聞いたところ、ミースは、それが受け入れられないならば設計を下りるといったという。結局ミースは自分の意にかなう実施設計を行い、グレーテは1929年4月にブルノ市に建築申請を出した。
工事は、ブルノのアイズラー兄弟社によって1929年6月にはじまり、工期が予定より延びたものの、1930年12月にトゥーゲントハット夫妻は新居に引っ越した。家具はミースと彼のパートナーのリリー・ライヒ(1885-1947)が担当し、ライヒはテキスタイルを一任された。広大な庭のデザインはミースと造園家グレーテ・ローダーによる。
グレーテとフリッツの期待を超える家になったが、トゥーゲントハット家がそこで暮らせたのは7年あまりにすぎなかった。ナチスによる1938年3月のオーストリア併合を機に、ホロコーストを避けるためにブルノにとどまるのを断念し、急遽飛行機でスイスに亡命し、その後ヴェネズエラに移住した。1938年にはゲシュタポがこの建物を接収し、1942年にドイツ第三帝国の財産とされた。第二次大戦中には爆撃を受け、床から天井までの窓ガラスが1枚を残して破壊され、家具やバスタブなどが盗まれた。その一方で間仕切壁が増設され、煙突が高めに変更された。戦後チェコ軍がこの建物を一時使用した際には、床のリノリウムが傷められた。1945年から50年まではダンス・スクールがこの建物を使い、1950年にはチェコの国家財産に組み入れられ、1962年に南モラビア健康管理局の管轄になって、1979年まで脊椎損傷の子供たちのリハビリ施設として使われた。
1963年に国の文化財に指定されたのがこの建物保存の第一歩で、1980年にブルノ市の所有になって、1981年から85年にかけて最初の修復が行われたが、そのときまで1枚だけ残っていた、可動の大判ガラスを廃棄してしまうなど、問題もあるものだった。1992年にトゥーゲントハット家の娘のひとりのダニエーラが、母の遺志を継いでこの住宅を公開してその重要性をアピールすることを訴えた。チェコの建築家もそれを支援し、翌1993年にブルノ市は公開に合意し、それにあわせての修復を決めた。その資金を集めるファンドが設立され、1994年から建物の公開がはじまった。
2001年には世界遺産に登録され、2003年から05年にかけて修復のための詳細な調査が行われ、それをもとに2006年にチェコの修復専門家を中心に修復計画がまとめられた。当初の状態に復原する工事は2010年から12年にかけて行われた。その復原の目的は竣工時の姿を再現することで、あたかも当時の居住者がいるかのような状態で見せるために家具などを再製し、1日あたり150人をめどにガイド・ツアーで見せることを前提に、受付やミュージアム・ショップ、そして展示スペース確保のために、一部の部屋を改変した。なお、食堂を囲っていたエボニー(黒檀)の半円状の壁が1940年代前半にゲシュタポによって剥がされ、マサリク大学法学部のバーの壁に転用されていたことが2011年に判明し、修復の際に当初の場所に戻された。また、建物を長期間維持するために、当初の設計の問題点(陸屋根の雨仕舞など)も改善されることになった。ちなみに、復原の際に建物がテラス方向に少しねじれていることがわかった。

写真2 トゥーゲントハット邸からの眺め

写真3 道路側外観

写真4 玄関ホール

写真5 グレーテの寝室

写真6 子供室前テラス

写真7 居間

写真8 温室

写真9 空調吹き出し口

写真10 食堂

写真11 オニックスの間仕切

写真12 オーニング開閉装置
トゥーゲントハット邸の設計趣旨
トゥーゲントハット邸はチェルノポルニ通りからの下り斜面(約2寸3分勾配)に建っており、敷地面積は7,363㎡もある。グレーテの父アルフレッド・レウ=ベーア(1872-1939)の所有地でブドウ畑になっていたのを、財産分与ということで娘に与えたものである。そこからはブルノ市を眼下に見晴らせ、はるか遠くには城も望めるという景勝の地である(写真2)。主体構造は鉄骨で、床は鉄筋コンクリート造で3層になっているが、下り斜面に建っているので、通りからは平家のように見える(写真3)。その最上階には、玄関(写真4)と、家族の個室(写真5)、家庭教師の部屋や浴室が並び、ガレージと運転手室がある別棟が付属している。その下が主階で、居間や食堂、台所、女中室などがある。最下階は裏まわりで、洗濯室や毛皮乾燥室、機械室、倉庫が並ぶ。建築面積は1,211㎡、延床面積は約2,000㎡で、子持ちの若夫婦の邸宅(子供の家庭教師やメイド、運転手も同居していたが)にしてもかなり大規模である。ワン・ルームの居間部分だけでも280㎡ある。建設費についての記録はないようだが、事実上、費用お構いなしということになったらしい。
この建物に入ってまず感じるのは、快適に住める家だということである。個室はさほど広くはないが、造りつけの大きな収納があり、夫婦用と子供・家庭教師用のバスルームが別々に備えられている。息子たちの部屋には洗面台までついている。そして、どの部屋からも、テラスを介して南に広がる緑や街の景色を楽しめる。子供室前には遊び場としての広いテラスがあり、砂場まで用意されている(写真6)。
主階の主要部はワン・ルームで、広大な居間は開放感にあふれている(写真7)。それは、南面から東面にまで連続する、床から天井までの大きな開口によるところが大きい。その南面中央の3枚のガラスのサイズは約4.9m╳2.8mで、厚さは1cm弱である。居間東側では全面ガラス壁が2列になって、その間が温室になっている(写真8)。よく知られているように、南面中央の大判ガラスの両側に配された2枚の大判ガラス窓は電動で下の階に引き込まれ、完全解放できるようになっている。ミースはその圧倒的な開放感を損なわないために、それらの窓の手前に手摺をつけるのを拒否した。今そこに見える低い手摺は、竣工後にトゥーゲントハット夫妻がつけたものである。ちなみに、その床に水平に走るパイプはガラスの結露防止の暖気を流すもので、それだけはミースが許容した。
この住宅には最初から空調が装備されていた。ヨーロッパの独立住宅では最初の導入例とされるもので、おもに暖房用である(冷房では霧状の水を噴射)。空気取り入れ口は最上階床下の道路側にあり、そこから外気が地下に導かれ、オイルと木のチップのフィルターを順にくぐったあと、加熱・冷却され、送風機で運ばれる。主階の居間北側の壁にその吹き出し口が見える(写真9、玄関ホールや個室にはラジエータを設置)。
目地が目立たないフラットな床と天井も開放感を高めるのに効いている。床を薄クリーム色のリノリウム敷きにしたのも、その平面の抽象性を強調したいためである。居間の広大なスペースは、必要に応じてカーテンで仕切ることができる。
クローム・メッキの板で包まれた十字形柱も、空間の開放感や浮遊感に寄与している。十字形なのでほっそりとして見えるだけでなく、その表面が周囲を映すので見た目の重さが消える。その内部にはスチールの板3枚が十字形に組み合わさっている。うち1枚が差し渡しで、短い2枚がその両側に直交するかたちで置かれ、その十字形の四隅に配されたアングル材とともに、ボルト締めで一体化されている。玄関脇の階段部分の独立柱の幅は236mmである(下階に行くほどその幅は大きくなっている)。ちなみに、この鉄柱は、ブルノの業者ではできないということで、ドイツでつくられた。
半円形のエボニー(インドネシア・セレベス島マカッサル産)の壁で区切られた食堂には、円形のテーブルがある(写真10)。これは3重の同心円状になっていて、中央の円盤の周囲に大小のドーナツ状のテーブル2つを順に置くことで人数の変化に応じられるというものである。
居間東側の中央部にはオニックスの間仕切がある(写真11)。バルセロナ・パヴィリオン(1929)でも使われたもので、ミースは最上のオニックスを使うためにドイツ中を探し回り、豪華客船に使われる予定だったものを手に入れて、模様のいい断面を得るためにその切断にも立ち会ったという。ミースは、構成要素を限定するぶん最高級の素材にこだわっていたということで、それがインテリアを引き立てるのに効いている。玄関ホールやテラスなどに張られた厚いトラヴァーティンも高級感の演出に寄与している。
子供室のものを除き、家具はすべて特注で、椅子は、緑の革張りのバルセロナ・チェアや、パイプに白い革を張ったブルーノ・チェア、そしてベージュの革張りのトゥーゲントハット・チェアなどである。
天井縁までタイル張りになった台所は広く、清潔感があり、その大きな窓からも南側に開ける景色が望める。大勢の客を接待することを想定してか、パントリーも巨大で、床から天井までの収納棚が並んでいる。
外壁は白セメント塗で、スチール・サッシュは外側が紺色に、室内側は薄クリーム色に塗られている。道路側で印象的なのは玄関脇のカーブした艶消しガラス壁で、そのカーブの奥まったところに玄関ドアがさりげなくついている。本館と別棟との間は抜けていて、細い無垢のスチール製の柵の向こうにテラスにつながるデッキが見える。この開口が、道路側に低く長く伸びるこの立面に変化を与えている。庭側の立面は3層で、内部の空間のあり方がそのまま立面に反映している。主階の立面は横長連続の大きな開口で占められ、最上階では連続するテラスの手摺の向こうに個室がかいま見える。最下階は鉄扉が1枚あるだけの一面の壁で、その西側面の幅広の外階段が、建物東側の斜面と呼応して、シンプルな立面に変化を与えている(写真1)。その外階段の上は広いテラスで、主階の室内から直接アクセスでき、戸外の居間という趣になっている。機能的にも意味がある要素を立面にアクセントを与える要素にもしているわけで、巧みな手法といえる。
主階のガラス窓の上にはオーニングが並び、細いスチールの腕木が縦方向のサッシュのレールを上下してオーニングを開閉する(写真12)。当初の腕木は風の吹き上げに対抗できず、じきに動かせなくなっていたようである。これは無垢の材と思われるが、それでも強度が不足していたということで、それはミースがそれを含め、部材を極力スレンダーにしたいと考えていたことを示している。2010年からの修理でも、当初のデザインを尊重してその細さは踏襲されているが、開け閉めは電動に変更された。
モダニズム建築の保存
これまで同時期のミースの代表作としてはもっぱらバルセルナ・パヴィリオン(1929)が評価されてきたが、トゥーゲントハット邸は、そのコンセプトを実際の住宅に適用し、その有効性を実証した点で、また快適に住めるものに仕立て上げた点で、より建築的で、注目すべきものである。この建物は、モダニズム建築の保存についても大きな示唆を与える。実は外装を含め、ほとんどレプリカといっていいほど、部材は取り替えられている。しかしそれは当初の設計趣旨やディテールを調度に至るまで徹底的に調べ上げ、ガイド付きツアーで公開することを前提に、当初の状態をできるだけ再現することにつとめた結果で、そのポリシーが明確で、それをもとに再現を正当化するロジックをつくりあげたことが評価される。特に調度もできるだけ再現したのが注目すべき点で、1985年の修理直後の写真と比べると、この空間構成において調度がいかに重要かが理解できる。
この「保存」では、建物についての記録がかなり残っており、グレーテ・トゥーゲントハットが1969年に受けたインタビューでさまざまな情報を伝え、それらをもとに包括的かつ徹底的な調査が行われたのがいい結果につながった。さらには、周囲の状況が当初とさほど変わっておらず、これからも変わる可能性が少ないことも、この「保存」の意義を高めているといえよう。このように好条件が揃っていたわけだが、数奇な運命を経て、かなり傷んでいたものをほとんど竣工時の姿に戻すのは並大抵のことではなかったはずで、レプリカに近いとはいえ、ここまで徹底してやられると大きな説得力があることを認めないわけにはいかない。

藤岡 洋保(ふじおか・ひろやす)
東京工業大学名誉教授
1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞
1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞