第44回東京建築賞入選作品選考評
宮崎 浩(東京建築賞選考委員会委員長、プランツ・アソシエイツ主宰)
平倉 直子(東京建築賞選考委員会委員長、平倉直子建築設計事務所主宰)
岡本 賢(東京建築賞選考委員会委員長、(一社)日本建築美術工芸協会会長)
永池 雅人(東京建築賞選考委員会委員長、(株)梓設計常務執行役員)
山梨 知彦(東京建築賞選考委員会委員長、(株)日建設計常務執行役員)
車戸 城二(東京建築賞選考委員会委員長、(株)竹中工務店常務執行役員)
渡辺 真理(東京建築賞選考委員会委員長、法政大学デザイン工学部建築学科教授)
宮原 浩輔(東京建築賞選考委員会委員長、(株)山田守建築事務所代表取締役社長)
金田 勝徳(東京建築賞選考委員会委員長、(株)構造計画プラス・ワン会長)
平倉 直子(東京建築賞選考委員会委員長、平倉直子建築設計事務所主宰)
岡本 賢(東京建築賞選考委員会委員長、(一社)日本建築美術工芸協会会長)
永池 雅人(東京建築賞選考委員会委員長、(株)梓設計常務執行役員)
山梨 知彦(東京建築賞選考委員会委員長、(株)日建設計常務執行役員)
車戸 城二(東京建築賞選考委員会委員長、(株)竹中工務店常務執行役員)
渡辺 真理(東京建築賞選考委員会委員長、法政大学デザイン工学部建築学科教授)
宮原 浩輔(東京建築賞選考委員会委員長、(株)山田守建築事務所代表取締役社長)
金田 勝徳(東京建築賞選考委員会委員長、(株)構造計画プラス・ワン会長)
首都高沿い昭和通りに面した神田和泉町YKK旧本社ビルの建替計画である。通り越しに見る特徴的なメインファサードは、繊細なアルミ押出材をファブリックのように立体的に組み合わせた60m×35mの1枚のスクリーンが宙に浮き、建築のアイデンティティを示しながら軽やかな街の風景を生み出している。このスクリーンは、西日を効果的にカットしながら、外部からの視線を絶妙にフィルタリングすることで、心地よい内部スペースの実現に大きく寄与している。昭和通り沿いの歩道からこの建物に近づくと、半透明だったスクリーンが一転、一枚の金属の面となって現れる。とても20,000㎡を越す本社ビルとは思えない、まちなみに対してヒューマンなスケールの透明な1階エントランスゾーンとの関係は新鮮である。
平面計画は、テナントビルの効率重視の計画とは異なり、エレベータや階段などの縦動線を分散させながらも見通しのよいワークスペースを生み出し、4階から屋上までをつなぐ階段が、本社オフィスならではのフロアを越えた協働作業やコミュニケーションの場を生み出している。この点も高く評価したい。
特筆すべきは、大掛かりで特殊な設備システムを用いずに高いレベルの省エネルギー性能と快適性を実現したことで、日本のオフィスとして初めてLEEDプラチナ認証を取得し、これからのクリーンビルディングの開発モデルを示した点にある。大都市における建築のあるべき姿を示す東京都知事賞に相応しい作品である。
駅より雪道を歩き、町の中心「札の辻」に移転した庁舎に至る。街並みのスケールに合わせた低層部と、晴れた空に同化するガラスのファサードが凛として爽やかである。
迎えてくれた役所や市民の方々は、2方開放型の大空間「札の辻広場」で毎週イベントを企画運営していると目を輝かせ、ホールなどに置かれた家具は、若者たちで埋まっていた。本来の行政・議会機能に加えた市民の居場所は、プロポーザルコンペ時の提案が遂行され、活かされている。
種々の機能を満たす空間計画の目論みは、構造・設備・環境・デザインを駆使した挑戦的な取り組みによって、新しい市庁舎としての公共建築が実現し、また周到に計画されたしきり方や備品によって、その多様な使い方も十二分に発揮されるであろう。
敷地はL字型で決して十分な広さとはいえないが、道路に面する外壁の長さが、市民広場の独立性と存在感を示し、思い切った魅力ある提案に繋がっている。なぜか似たような庁舎計画が立ち上がる昨今、唯一無二の回答は一石を投じるものであり、東京都建築士事務所協会会長賞にふさわしい。
「庁舎建設に関わるパートナー(発注者、利用者、設計者、施工者)夫々が立場に応じた責任と情熱を持ち、シンプルに取り組むことである」ということを、改めて確認しここで伝えたい。また、設計者は、調査研究を通じて以前より町に関わっていたことも書き添え、その日常の研鑽にも敬意を評す。
鎌倉の八幡宮神社のすぐ脇の丘陵地に古くから開発された20軒ほどの住宅地の一画が、この住宅の敷地である。この土地の特徴は、車輌でのアプローチがまったくなく、狭い急峻な階段を登っていくしかないことである。そのために建設は資材のすべてを人力で運び上げたという。そのために極力シンプルな構成が必要であったと思われる。
平面は約7m×7mの正方形で、各辺の外周に2本ずつ計8本の鉄骨柱によって主構造をつくり、無柱空間を実現している。1階にエントランス、浴室、トイレ、寝室、収納スペース等を配し、外部に対し閉じた空間をつくっているのに対し、2階のリビング、ダイニングは四方をフルオープンにして周辺の濃い緑の風景を充分に取り込んでいる。特徴的なピラミッド形状の高い天井と軒高を低く抑えた室内空間は、包み込まれるような落ち着きと安心感を与えてくれる。カーテンボックスから天井上部へ導く排熱システムや、夜間電力利用の床蓄熱、蓄熱ガラスの採用などさまざまな省エネルギーのアイデアを盛り込み、建築家の自邸であるがゆえに可能になったデザインへのこだわり、思い入れが随所にみられる優れた建築作品である。
都心にありながら閑静な住宅地に立つ戸建住宅である。正面のファサードはコンクリートの壁に開口をあけたシンプルなデザインで、その後ろに中庭空間を内蔵しているため、通りからの視線は遮られている。敷地が道路から1層分高いため、通りに面した駐車場は地下扱いとなり、住居は地上2階建てとなる。
内部は2層吹き抜けのワンルーム的な空間で、この吹き抜けを中心に家族の生活が展開される。1階はリニアに展開する機能空間の先に中庭があり、中庭の先に設けた壁の開口は、あたかも劇場のプロセニアムアーチのごとくその先の風景を切り取っている。2階は吹き抜けに面してカウンターが設置され、子供たちの勉強スペースや夫婦の作業スペースとして活用されている。ただ大胆な階段にはやや不安を感じる。
内部は打ち放し仕上げであるが、外断熱のため冷たさは感じられない。また形態制限を巧みにクリアしたハイサイドライトからは、隣家の視線を遮りながら豊かな光を取り入れている。このあたりは住み手の強いこだわりも反映されており、住み手と設計者のコラボレーションにより気持ちのよい空間が演出されている。
都心の住宅地に計画された、長屋形式の集合住宅の計画である。
間口が狭く奥行きが深い敷地に、アプローチのための通路を片方に寄せて取り、残りのL字型の部分に3軒のメゾネット住宅を納めている。各部屋2面以上の開口から採光と通風を取り込むために、住戸間の戸境壁は平行ではなく放射状に配されていて、それが各戸の内部空間を特徴づけているところが巧みである。スタイリッシュな内部空間は、写真で見る限り生活感を感じさせないのだが、実際に部屋を見学させていただくと、若い世代は意外に上手に住みこなしていたのも好印象であった。
若い世代がこうした住居をまるで衣服を脱ぎ着するかのように移り住む生活様式は、あるボリュームを持ったマーケットを生み出しているようだが、そろそろこうした特定世代に特化した居住空間をフローとしてつくるトレンドの中にも問題が見え始めているようにも感じる。10数年後には、かつて木賃住宅ゾーンが抱えたような問題を、こうした住宅群がカタチを変えて抱え込みはしないだろうか。口当たりよくデザインされた住まいが、建築家によってあまりにも無批判に提供されてはいないだろうか、といった心配が脳裏をかすめた。
少々難ありの敷地に対して賃貸集合住宅を提案し、低評価の土地から収益を生み出すことで出資を募るのが設計者のビジネススキームとうかがった。ここでは具体的には床も含めて「最低限」の躯体と設備を構築した時点、つまり通常よりは一歩手前で仕上げを止めて後は居住者の発想に委ねるという仕組みとなっている。通常、ここに模範解答的な家具レイアウトを参考提案するまでが建築家の役割だが、上手く住んでもらえそうな人に、住むためのヒントを提供しながら入居斡旋していくことまで行っている。ある入居者の住まいを拝見したが、たとえば設計者が螺旋階段と壁との間に微妙な距離をとり、ここに入居者が見事に収納小物のレイアウトで反応するなど、建築の持つインスピレーションと応答しながら、むしろ思いがけないほどセンスよく住まわれていることに脱帽した。この結果を導くために普段から入居者との会話を大切にしながら次の設計に生かしているとのことであり、建築家の仕事を「よりよい住環境を生み出すこと」とすれば、自分たちのデザインだけでなく、入居者というマーケット側とのコラボという、通常賃貸住宅では起こらない仕組みと、それにふさわしいデザインを提案していることが評価された。
稠密なコンクリートのビルに取り囲まれた都心付近では、木造の外観は際立って優しい。高さ10mほどの建物に囲まれた中庭アプローチや外周は、建物の高さ方向の分節と、丁寧で自然な風合いのランドスケープの助けも借りて、たいへん心地よく、稠密環境に住むことへのひとつの提案となっている。人や車の通りが多い地上階は、RC造を少し沈めて1階の軒線を低く抑えオフィス・店舗としている。この上の2、3階を住宅にするという伝統的下駄履き住宅の構成を踏まえながら、住宅部分のファサードは横向きの連子といえそうな細かな木製ルーバーで全体を覆う抽象的な意匠で、アノニマスな環境との間を巧みに調停している。木材を製材前の丸太で購入して使用箇所を割り当てるといった、価格面まで行き届いた木造実現へのこだわり、細部まで行き届いたデリケートなスケール感への配慮が巧みで、木造としての魅力を都市環境の中に十分に印象付けていることが評価された。ただ、このプログラムの常として、課題となる内から外への開放性と、外から内へのプライバシーのバランスについて、ルーバーに囲まれた屋上庭園はやや暗く、ここにもう少しの工夫があればさらに魅力的になったのではと感じたのは欲張りすぎであろうか。
野田市郊外のこの辺りはゴルフ場が密集している。そのひとつ、千葉カントリ―クラブ梅郷コース内にわれわれの乗った車が彷徨い込んでいくのでどうなることかと思っていると、やがて開けた霊園に出た。梅郷礼拝堂はこの霊園の中心施設である。延床面積200㎡ほどのY字型の空間を6種18本の組柱で架構している。現地に行くまではこの内部空間がイメージしきれなかった。設計者のいう「玉すだれ」状の木架構が建物規模にしては大げさなものではないかと気になっていたのである。しかし、現地で確認するとそれが杞憂だということがわかった。組柱はそのほとんどに105mm×105mm角の製材(ヒノキ)が用いられているが、互いにもたれあうように架構された内部空間(幅員約7m、構造スパン約6m)は、このような架構が新奇なものであるにも関わらず、木造空間としてとても自然なものに感じられた。銅板一文字葺の屋根も見事な出来で、Y字型の平面形をエレガントに隆起させた屋根形状が、余計な細部意匠なくして表現されているのが気持ちよい。軒先の薄さが屋根に軽やかな印象を与える。3つのスロープが出会う屋根頂部は「巻きハゼを用い、釣り子をハンダで固定した」という説明を受けたが、ハンダの一部は設計者自らセルフビルドしたとのことである。設計者が建設行為に積極的にコミットし、専門職の職人がそれに喚起されて設計と施工が一体となったものづくりが行われるという、幸福な関係性が建物に滲み出ているように思われた。稀有な作品である。
当初は美術品の収蔵保管のための施設として計画がスタートしたが、住宅や多くの学校に囲まれている立地環境であることからアート教育普及活動の機能も求められるようになり、最終的にライブラリーやホールが付加されたアートリサーチセンターとして結実した。単なる収蔵庫ではなく、美術文化普及の拠点として情報発信、アクティビティの場に相応しい建築空間のデザインが求められたわけである。
交通量の多い幹線道路に面する敷地であるが、アプローチ周りの巧みな建築的工夫により落ち着いた外部空間が創出されている。収蔵庫とライブラリーのコンクリートの塊と、水平線を強調する車寄せや繊細な縦ルーバーがつくり出す端正なエレベーションとの対比が美しい。エントランスホールは、中庭への開放感を確保しつつ適切に環境がコントロールされた上質な空間で、収蔵庫のそれとは思えない。
この施設の目玉のひとつがバックヤードツアーである。セキュリティを確保しつつ、自然な動線で来館者が修復作業を見学できるよう建築的な配慮がなされている。
プロジェクトの進捗に伴い設計者側が発注者とともに考えを深め、徐々に建築計画がブラッシュアップされており、顧客との適切なコミュニケーションの観点からも建築士事務所の職能が高いレベルで発揮されており高く評価できる。優秀賞に相応しい作品である。
北側に北陸新幹線が走り、南側は国道18号線に面した敷地に建つ、農機具メーカーのショウルームである。そこは郊外の幹線道路サイドによく見られる、自動車のショウルームやモールが建ち並ぶ街並みとは異なり、前面の国道を走る車以外に人影もほとんど見られない、緑豊かな農村の一角という風情である。
そうした環境の中にあるこのショウルームは、適度の高さと厚さをもって水平に広がる大屋根と、それを支えるための構造要素でもある数段の棚で構成されている。見える範囲の縁から縁まで、途切れることのなく垂直・水平の木材で構成されている。その木材は地色のまま仕上げられていて、それらとカラフルにデザインされた小型農機具との対比が、清々しく、潔さを感じさせる。
構造は軒先の鉄骨柱を除いて、仕上げと構造部材を兼ねた木材を用いた木質構造である。構造形式は比較的大スパンの屋根梁以外は、120mm × 120mmの小径集成材と構造用合板を組み合わせたサンドイッチパネルで構成されていて、その単純明快さがこの建築物の清々しさを強調している。
「なぜ木質構造に?」という問いに対して、「コストがなかったから」との答えの率直さも十分納得できる。不必要に力むことなく、さりげない仕上げのあり方や、居住空間の環境にもきちんと配慮した設計力は高く評価される。
東京の都心において、高層ビルに構える旅館としての、新しいかたちを生み出すことを目指した作品である。
高層ビルでありながら、まず玄関で靴を脱ぎ、全館を裸足で楽しんでもらおうとの姿勢。高層ビルの各フロアの孤立性を逆手に取り、各階をひとつの小さな旅館としてまとめた構成。奇をてらった演出にも見えかねないこれらのコンセプトを、地に足ついた心地よい内部空間にまとめ上げている点が見事である。
たとえば、玄関では膨大な数の下駄箱を巧みにデザインして、無理なくファサードの一部に昇華しているし、ホテルで気になる廊下に立ち並ぶPSの扉も、ここでは美しい明かり障子へと組み替えられている。さらには、外国映画の中の日本建築にでも出てきそうな「畳敷きの廊下」といったボキャブラリーが、経験に裏打ちされた手腕で建築化されている。表面上の繊細さの裏に、建築家が手掛けた内装空間ならではの、骨太な思想といったものの存在すら感じられ、泊まってみたいという思いを掻き立てられる空間に仕上がっている。
一方で、外観、特に周辺建物とのあり方には、少々疑問を感じた。素っ気なさは狙いなのであろうが、内部に見られた巧みさが欠けているようにも感じられた。
八ヶ岳の麓、森の中に静かに佇む集会場の計画である。敷地に足を踏み入れると、屋根付きの屋外ロビーがホールへと導いてくれる。ふと横を見ると、中庭を囲むように配置されたホール、カフェ、多目的ホールといった配置の構図が見えてくる。まさに設計者が心を傾けた空間ではなかろうか。
外装には森への思いがそこかしこに見て取れる。アスロックにペイントされた樹木の枝張りのようなパターン、開口部に取り付けられたやはり樹木を模したアルキャストによるルーバー。森に溶け込む建築を目指したとのことだが、残念ながらそのボリューム感まではカバーできなかったようだ。
内部に入るとシンプルで禁欲的な空間が迎えてくれる。催し物の際には観客が主役になれる空間である。ホールという本来閉鎖的な機能に対し、周辺環境を最大限活かし、森に向けて開いた大きなガラス面は心地よい空間を演出している。しかしながら熱負荷に配慮して採用したLow‐Eガラスが、森へのクリアな視界をやや妨げている感があるのが残念である。それにもまして、今回現地審査が木々が葉を落とした冬であったことが、この建物にとっては最も残念であったかもしれない。
平面計画は、テナントビルの効率重視の計画とは異なり、エレベータや階段などの縦動線を分散させながらも見通しのよいワークスペースを生み出し、4階から屋上までをつなぐ階段が、本社オフィスならではのフロアを越えた協働作業やコミュニケーションの場を生み出している。この点も高く評価したい。
特筆すべきは、大掛かりで特殊な設備システムを用いずに高いレベルの省エネルギー性能と快適性を実現したことで、日本のオフィスとして初めてLEEDプラチナ認証を取得し、これからのクリーンビルディングの開発モデルを示した点にある。大都市における建築のあるべき姿を示す東京都知事賞に相応しい作品である。
選考委員|宮崎 浩
迎えてくれた役所や市民の方々は、2方開放型の大空間「札の辻広場」で毎週イベントを企画運営していると目を輝かせ、ホールなどに置かれた家具は、若者たちで埋まっていた。本来の行政・議会機能に加えた市民の居場所は、プロポーザルコンペ時の提案が遂行され、活かされている。
種々の機能を満たす空間計画の目論みは、構造・設備・環境・デザインを駆使した挑戦的な取り組みによって、新しい市庁舎としての公共建築が実現し、また周到に計画されたしきり方や備品によって、その多様な使い方も十二分に発揮されるであろう。
敷地はL字型で決して十分な広さとはいえないが、道路に面する外壁の長さが、市民広場の独立性と存在感を示し、思い切った魅力ある提案に繋がっている。なぜか似たような庁舎計画が立ち上がる昨今、唯一無二の回答は一石を投じるものであり、東京都建築士事務所協会会長賞にふさわしい。
「庁舎建設に関わるパートナー(発注者、利用者、設計者、施工者)夫々が立場に応じた責任と情熱を持ち、シンプルに取り組むことである」ということを、改めて確認しここで伝えたい。また、設計者は、調査研究を通じて以前より町に関わっていたことも書き添え、その日常の研鑽にも敬意を評す。
選考委員|平倉 直子
平面は約7m×7mの正方形で、各辺の外周に2本ずつ計8本の鉄骨柱によって主構造をつくり、無柱空間を実現している。1階にエントランス、浴室、トイレ、寝室、収納スペース等を配し、外部に対し閉じた空間をつくっているのに対し、2階のリビング、ダイニングは四方をフルオープンにして周辺の濃い緑の風景を充分に取り込んでいる。特徴的なピラミッド形状の高い天井と軒高を低く抑えた室内空間は、包み込まれるような落ち着きと安心感を与えてくれる。カーテンボックスから天井上部へ導く排熱システムや、夜間電力利用の床蓄熱、蓄熱ガラスの採用などさまざまな省エネルギーのアイデアを盛り込み、建築家の自邸であるがゆえに可能になったデザインへのこだわり、思い入れが随所にみられる優れた建築作品である。
選考委員|岡本 賢
内部は2層吹き抜けのワンルーム的な空間で、この吹き抜けを中心に家族の生活が展開される。1階はリニアに展開する機能空間の先に中庭があり、中庭の先に設けた壁の開口は、あたかも劇場のプロセニアムアーチのごとくその先の風景を切り取っている。2階は吹き抜けに面してカウンターが設置され、子供たちの勉強スペースや夫婦の作業スペースとして活用されている。ただ大胆な階段にはやや不安を感じる。
内部は打ち放し仕上げであるが、外断熱のため冷たさは感じられない。また形態制限を巧みにクリアしたハイサイドライトからは、隣家の視線を遮りながら豊かな光を取り入れている。このあたりは住み手の強いこだわりも反映されており、住み手と設計者のコラボレーションにより気持ちのよい空間が演出されている。
選考委員|永池 雅人
間口が狭く奥行きが深い敷地に、アプローチのための通路を片方に寄せて取り、残りのL字型の部分に3軒のメゾネット住宅を納めている。各部屋2面以上の開口から採光と通風を取り込むために、住戸間の戸境壁は平行ではなく放射状に配されていて、それが各戸の内部空間を特徴づけているところが巧みである。スタイリッシュな内部空間は、写真で見る限り生活感を感じさせないのだが、実際に部屋を見学させていただくと、若い世代は意外に上手に住みこなしていたのも好印象であった。
若い世代がこうした住居をまるで衣服を脱ぎ着するかのように移り住む生活様式は、あるボリュームを持ったマーケットを生み出しているようだが、そろそろこうした特定世代に特化した居住空間をフローとしてつくるトレンドの中にも問題が見え始めているようにも感じる。10数年後には、かつて木賃住宅ゾーンが抱えたような問題を、こうした住宅群がカタチを変えて抱え込みはしないだろうか。口当たりよくデザインされた住まいが、建築家によってあまりにも無批判に提供されてはいないだろうか、といった心配が脳裏をかすめた。
選考委員|山梨 知彦
選考委員|車戸 城二
選考委員|車戸 城二
選考委員|渡辺 真理
交通量の多い幹線道路に面する敷地であるが、アプローチ周りの巧みな建築的工夫により落ち着いた外部空間が創出されている。収蔵庫とライブラリーのコンクリートの塊と、水平線を強調する車寄せや繊細な縦ルーバーがつくり出す端正なエレベーションとの対比が美しい。エントランスホールは、中庭への開放感を確保しつつ適切に環境がコントロールされた上質な空間で、収蔵庫のそれとは思えない。
この施設の目玉のひとつがバックヤードツアーである。セキュリティを確保しつつ、自然な動線で来館者が修復作業を見学できるよう建築的な配慮がなされている。
プロジェクトの進捗に伴い設計者側が発注者とともに考えを深め、徐々に建築計画がブラッシュアップされており、顧客との適切なコミュニケーションの観点からも建築士事務所の職能が高いレベルで発揮されており高く評価できる。優秀賞に相応しい作品である。
選考委員|宮原 浩輔
そうした環境の中にあるこのショウルームは、適度の高さと厚さをもって水平に広がる大屋根と、それを支えるための構造要素でもある数段の棚で構成されている。見える範囲の縁から縁まで、途切れることのなく垂直・水平の木材で構成されている。その木材は地色のまま仕上げられていて、それらとカラフルにデザインされた小型農機具との対比が、清々しく、潔さを感じさせる。
構造は軒先の鉄骨柱を除いて、仕上げと構造部材を兼ねた木材を用いた木質構造である。構造形式は比較的大スパンの屋根梁以外は、120mm × 120mmの小径集成材と構造用合板を組み合わせたサンドイッチパネルで構成されていて、その単純明快さがこの建築物の清々しさを強調している。
「なぜ木質構造に?」という問いに対して、「コストがなかったから」との答えの率直さも十分納得できる。不必要に力むことなく、さりげない仕上げのあり方や、居住空間の環境にもきちんと配慮した設計力は高く評価される。
選考委員|金田 勝徳
高層ビルでありながら、まず玄関で靴を脱ぎ、全館を裸足で楽しんでもらおうとの姿勢。高層ビルの各フロアの孤立性を逆手に取り、各階をひとつの小さな旅館としてまとめた構成。奇をてらった演出にも見えかねないこれらのコンセプトを、地に足ついた心地よい内部空間にまとめ上げている点が見事である。
たとえば、玄関では膨大な数の下駄箱を巧みにデザインして、無理なくファサードの一部に昇華しているし、ホテルで気になる廊下に立ち並ぶPSの扉も、ここでは美しい明かり障子へと組み替えられている。さらには、外国映画の中の日本建築にでも出てきそうな「畳敷きの廊下」といったボキャブラリーが、経験に裏打ちされた手腕で建築化されている。表面上の繊細さの裏に、建築家が手掛けた内装空間ならではの、骨太な思想といったものの存在すら感じられ、泊まってみたいという思いを掻き立てられる空間に仕上がっている。
一方で、外観、特に周辺建物とのあり方には、少々疑問を感じた。素っ気なさは狙いなのであろうが、内部に見られた巧みさが欠けているようにも感じられた。
選考委員|山梨 知彦
外装には森への思いがそこかしこに見て取れる。アスロックにペイントされた樹木の枝張りのようなパターン、開口部に取り付けられたやはり樹木を模したアルキャストによるルーバー。森に溶け込む建築を目指したとのことだが、残念ながらそのボリューム感まではカバーできなかったようだ。
内部に入るとシンプルで禁欲的な空間が迎えてくれる。催し物の際には観客が主役になれる空間である。ホールという本来閉鎖的な機能に対し、周辺環境を最大限活かし、森に向けて開いた大きなガラス面は心地よい空間を演出している。しかしながら熱負荷に配慮して採用したLow‐Eガラスが、森へのクリアな視界をやや妨げている感があるのが残念である。それにもまして、今回現地審査が木々が葉を落とした冬であったことが、この建物にとっては最も残念であったかもしれない。
選考委員|永池 雅人
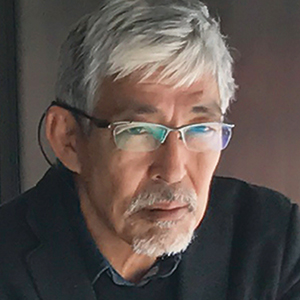
宮崎 浩(みやざき・ひろし)
1952年 福岡県生まれ/1975年 早稲田大学理工学部建築学科卒業/1977年 早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了/1977〜89年 株式会社槇総合計画事務所/1989年 株式会社プランツアソシエイツ設立/1990〜2010年 早稲田大学非常勤講師/2011〜13年 同大学大学院客員教授

平倉 直子(ひらくら・なおこ)
建築家、平倉直子建築設計事務所代表取締役
1950年 東京都生まれ/日本女子大学住居学科卒業/日本女子大学、関東学院大学、東京大学、他、非常勤講師
1950年 東京都生まれ/日本女子大学住居学科卒業/日本女子大学、関東学院大学、東京大学、他、非常勤講師

岡本 賢(おかもと・まさる)
建築家、一般社団法人日本建築美術協会会長
1939年東京都生まれ/1964年 名古屋工業大学建築学科卒業後、株式会社久米建築事務所(現・株式会社久米設計)/1999年 同代表取締役社長/2006年 社団法人東京都建築士事務所協会副会長/2014年 一般社団法人日本建築美術協会会長
1939年東京都生まれ/1964年 名古屋工業大学建築学科卒業後、株式会社久米建築事務所(現・株式会社久米設計)/1999年 同代表取締役社長/2006年 社団法人東京都建築士事務所協会副会長/2014年 一般社団法人日本建築美術協会会長

永池 雅人(ながいけ・まさと)
東京都建築士事務所協会副会長
1957年 長野県生まれ/1981年早稲田大学理工学部建築学科卒業後、梓設計入社、現在常務執行役員/品川支部
1957年 長野県生まれ/1981年早稲田大学理工学部建築学科卒業後、梓設計入社、現在常務執行役員/品川支部

山梨 知彦(やまなし・ともひこ)
建築家、株式会社日建設計常務執行役員 設計部門副統括
1960年 神奈川県生まれ/東京藝術大学美術学部建築学科卒業/東京大学大学院都市工学専攻修了/1986年 日建設計
1960年 神奈川県生まれ/東京藝術大学美術学部建築学科卒業/東京大学大学院都市工学専攻修了/1986年 日建設計
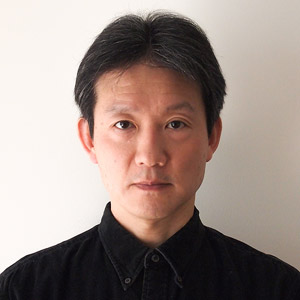
車戸 城二(くるまど・じょうじ)
建築家、(株)竹中工務店 常務執行役員
1956年生まれ/1979年 早稲田大学卒業/1981年 同大学院修了後、株式会社竹中工務店/1988年 カリフォルニア大学バークレー校建築学修士課程修了/1989年 コロンビア大学都市デザイン修士課程修了/2011年 株式会社竹中工務店設計部長/現在、同社常務執行役員
1956年生まれ/1979年 早稲田大学卒業/1981年 同大学院修了後、株式会社竹中工務店/1988年 カリフォルニア大学バークレー校建築学修士課程修了/1989年 コロンビア大学都市デザイン修士課程修了/2011年 株式会社竹中工務店設計部長/現在、同社常務執行役員

渡辺 真理(わたなべ・まこと)
建築家、法政大学デザイン工学部教授、設計組織ADH共同代表
群馬県前橋市生まれ/1977年 京都大学大学院修了/1979年 ハーバード大学デザイン学部大学院修了/磯崎新アトリエを経て、設計組織ADHを木下庸子と設立
群馬県前橋市生まれ/1977年 京都大学大学院修了/1979年 ハーバード大学デザイン学部大学院修了/磯崎新アトリエを経て、設計組織ADHを木下庸子と設立

宮原 浩輔(みやはら・こうすけ)
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会理事、一般社団法人東京都建築士事務所協会常任理事
1956年鹿児島県生まれ/1981年東京工業大学建築学科卒業後、株式会社山田守建築事務所入社/現在、同代表取締役社長
1956年鹿児島県生まれ/1981年東京工業大学建築学科卒業後、株式会社山田守建築事務所入社/現在、同代表取締役社長

金田 勝徳(かねだ・かつのり)
構造家、構造計画プラス・ワン会長
1968年 日本大学理工学部建築学科卒業/1968〜86年 石本建築事務所/1986〜88年TIS&Partners/1988年〜現在 構造計画プラス・ワン/2005〜10年 芝浦工業大学工学部特任教授/2010〜14年 日本大学理工学部特任教授、工学博士
1968年 日本大学理工学部建築学科卒業/1968〜86年 石本建築事務所/1986〜88年TIS&Partners/1988年〜現在 構造計画プラス・ワン/2005〜10年 芝浦工業大学工学部特任教授/2010〜14年 日本大学理工学部特任教授、工学博士
記事カテゴリー:東京建築賞
タグ:








